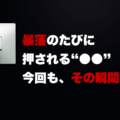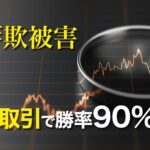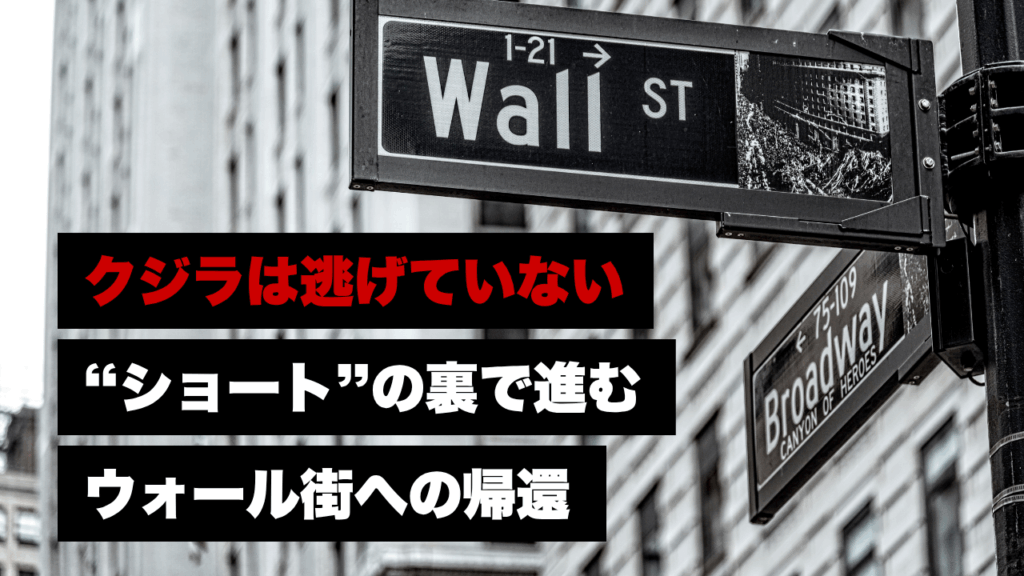
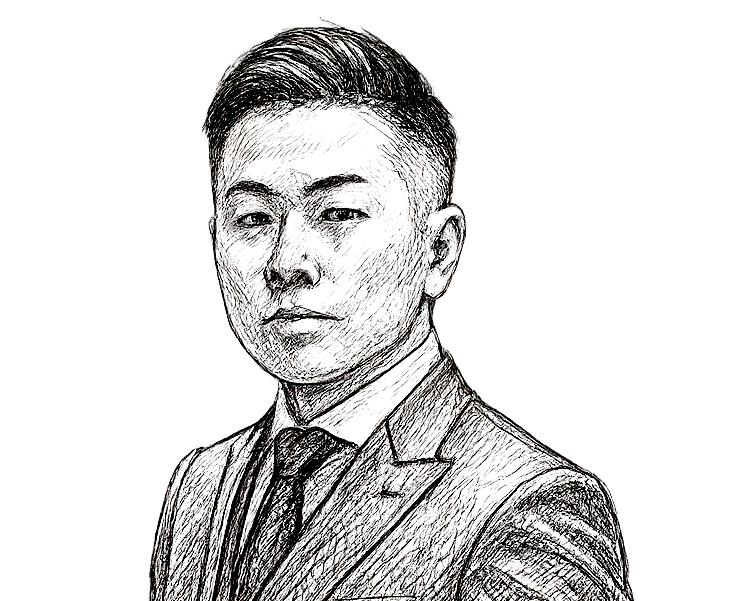
From.西山
「クジラがビットコインをショートしている」──
このニュースを見て、
ドキッとした人も多いと思います。
市場では、数億ドル規模のショートポジションが観測され、
「やっぱりもう天井か?」という声も上がりました。
でも、データをよく見ると、
実際の姿はまったく違います。
彼らは逃げているのではなく、
整えているのです。
クジラのショートは「退避」ではなく「リスク調整」
クジラたちは、
長期的に大量のビットコインを保有する
いわゆる“ロングプレイヤー”です。
そんな彼らがショートを取るのは、
「下落で儲けたい」からではありません。
市場が不安定なときに、
保有資産を守るためのリスクヘッジです。
たとえば──
長期保有のロングを持ったまま、
短期的にショート(空売り)を入れる。
もし価格が下がれば、ロングは含み損になりますが、
ショートで利益が出て全体の損失を抑えられる。
逆に価格が上がれば、
ショートは損でもロングが値上がりする。
つまり、どちらに転んでも
損を最小限にする“防御ポジション。
クジラたちは“相場から降りた”のではなく、
次の上昇に備えて体勢を整えている。
これが「市場からの撤退」ではなく
「リスク調整」と呼ぶ理由です。
実際、多くのアナリストは…
「過剰レバレッジの清算を伴う健全な調整」
と見ており、グラスノードのデータでも、
短期投資家は手放しても、
長期保有者(LTH)は動いていません。
売っていない。ただ、“場所”を変えただけ
そして注目すべきは、
ショートの後に見られた資金の移動です。
ブロックチェーン上の分析では、
ショートポジションが積まれた時期と同じタイミングで、
「クジラのウォレットから
ETF関連口座(コインベースなど)への
資金移動が増加している」
ことが確認されています。
つまり彼らは「売って逃げた」のではなく、
利益や保有資産の一部を金融システムの中へ移している。
ブラックロックのデジタル資産責任者、
ロビー・ミッチニック氏もこう語っています。
「ビットコインの大口保有者が、ブロックチェーンから
ウォール街の管理下に資産を移している」
「ブラックロックはすでに
30億ドル(約4600億円)の資産移転を支援した」
──つまり、“市場からの撤退”ではなく“ETF移行”。
この動きが顕著に現れているのです。
ETFが吸い上げる“クジラ資金”
そして、この動きを象徴しているのが、
アメリカで承認された現物ビットコインETFの存在です。
中でも、世界最大の資産運用会社ブラックロックの
IBIT(iShares Bitcoin Trust)は別格。
“ウォール街の正規ルートで
ビットコインに投資できる仕組み”
として、世界中の機関投資家の資金を
一気に集めました。
Bitboのデータによれば、
IBITは2024年6月時点で史上最速で700億ドルを突破。
いまでは880億ドル超に拡大しています。
ETF全体でも「流入」が続いており、
ビットコイン市場から資金は“出ていく”のではなく、
ETFという新しい器に移動している。
クジラたちは市場から離れたのではなく、
より整った“制度の中”に入ってきたのです。
結論:クジラは逃げていない。市場は成熟している。
ここまでをまとめると、こうです。
クジラのショートは、
下落を読んだ戦略的なリスク調整。
ETFへの資金移動は、
市場離脱ではなく制度への組み込み。
つまり、彼らは「売り抜け」ているのではなく、
相場の波を利用しながら、次の局面に備えて
資産の構造を変えている。
短期的には調整が続きますが、
その裏では“長期的な安定化”が静かに進んでいます。
ビットコイン市場はいま、
「投機の時代」から「制度の時代」へと確実に移行中。
かつて“反体制の象徴”だったビットコインが、
いまやウォール街の中で整然と管理され始めた。
──この流れを「終わり」ではなく
「進化」と捉えるべきでしょう。
ビットコインはいま、
“信用資産”としての新しいフェーズに入ったばかり。
本当の勝負は、ここからです。
追伸
先日、西山タイムズで配信した
“守りながら増やす方法”が大好評でした。
まだ聞いてなかったら、
一度メッセージをお送りください。
正会員限定【 公式LINE 】
正会員の皆様には特別な情報を
公式LINEでもお届けしております。
ご登録がお済みでない場合は、
今すぐこちらからご登録ください。
配信記事一覧【 バックナンバー 】
過去に配信した記事はすべて、
バックナンバーページにて確認可能です。
お問合わせ【 電話・メール 】
サポートデスクへのお問合わせは
電話、メールのどちらからでも承っております。
 投資の“KAWARA”版.com
投資の“KAWARA”版.com